先日から視聴し始めたNetflixの、「華流映画」カテゴリで探していたときに見つけたのがこちらの『点対点』(2014・香港)。
子どもの頃に海外へ移住し、また香港へ戻ってきた男、ウォン・シュー・チュン。小さいときに香港を出たからこそ、自分が知る「かつての姿の香港」への思い入れが強く、その「かつての香港」の記憶を子どもの頃に遊んだ「点繋ぎゲーム」の“点”として、気付かれないように街の中に残していた──
中国本土から北京語教師(字幕では「普通語」とされている)としてやってきた女、カオ・シャオシュ。香港が好きでやってきたわけではないため、香港にあまり興味がなく、部屋と職場の往復だけという生活──
ある日シャオシュが、チュンが描いた数カ所の「点」を見つけたことから、それぞれの人生が動きだし、お互いの「点と点」が繋がってゆく──
といった感じの物語。大きな出来事は起こりませんが、本人たちは気付かないすれ違いが何度もあったり、大丸デパートと校長先生の過去、点繋ぎゲームが載っていた雑誌『児童楽園』といったようなところで、二人を繋ぐ共通「点」があることや、「北京語を習う香港人のチュンと、北京語の教師で大陸人のシャオシュ」「変わりゆく香港の中にかつての香港を見つけようとするチュンと、かつての香港を記した“点”に引き寄せられて今の香港を巡り、知ってゆくシャオシュ」といったように、対のような立場である二人がお互い行動することによって近づいていくまでを「第一回戦」から「第三回戦」までの攻守交代的な押し引きでテンポよく描かれています。
70年代から繋がる点と点
まだお互いに相手のことを知らない同士の、点と点を結ぶやり取りの背景に、共通する人物との接「点」があったのでした。
シャオシュが勤める学校の校長先生は、70年代に大丸デパートで働いていた過去があり、1971年のある日、トイレへ行くため持ち場を同僚と替わってもらったときにガスの爆発事故が起きて、自分は助かったものの、持ち場を替わってもらった同僚が事故に巻き込まれて亡くなる、という悲しい過去を持っていた──
チュンはある日、大丸があった場所の前で自分と同じマフラーを巻いた校長先生を見てあとをつけて行き、それに気付いた校長先生とチュンとの会話で、おそらくお互いのことを知ったのだと思いますが、その時点ではまだ私たちは、校長先生とチュンの繋がりを知ることはできません。
そしてその大丸での爆発事故で、持ち場を替わったことで亡くなったウォン・ウェイフォンさんは、実はチュンのおばさんであったことが、校長先生の回想シーンでの当時の新聞記事と、チュンの回想シーンでの『児童楽園』を詰めた箱に書いてあった「シュー・チュンへ ウェイフォンおばさんより」というメッセージにより、映画を見ている私たちは知ることとなります。
11~12歳で香港を離れたチュンにとって、子どもの頃に過ごした「かつての香港」の思い出が強く残っている理由は、単に外国へ渡ってしまったからだけではなく、おばさんを事故で亡くした記憶も関係しているのかもしれません。
チュンが描いたそれぞれの点図は、かつて漁村だった駅には魚の絵、というようにそれぞれの地下鉄の駅と関係がある図柄になっていますが、大丸デパートがあった駅には都市ガスのロゴに似た火の絵柄が描かれていました。そしてシャオシュが最初に点図の謎を解いたのが、まさにその火の絵柄でした。そこで初めて最初の「点」と「点」が繋がったのです。
その他、見落としがちな細かい部分
チュンとシャオシュがニアミスする場面はたくさんあるのでここでは書きませんが、他にも細かいところで人と人が繋がっている箇所や、ちょっとした小ネタ的なものがありました。もしかすると一度見ただけでは気付かないかもしれません。
チュンとシンイーの映画デート(少なくともシンイーにとってはデートのつもりだった)の後、公園のベンチに座って話すもチュンにその気がないので会話がまるで続かない。そして会話が途切れるたびにカラスがカァと鳴くのが3回続く(笑)。
チュンの職場(デザイン事務所?)にいるデザイナーの白人男性アランと、シャオシュのルームメイトが友達だった。
退職したチュンが電話した相手は、以前にばったり遭遇した、かつて一緒にデモ活動をした女性。
英語タイトルはそのまんなの『DOT 2 DOT』ですが、シャオシュが点図を描いた人とコンタクトを取ろうとして取得した捨てアドがdot2dot@~。
まとめ
オープニングの小気味良い歌から始まり、香港という独特な場所を、賑やかで多国籍、近代的なものと古いものが入り交じった魅力的な街としてうまく描いている映画だなぁという印象でした。香港に行ったことがある人、住んでいたことがある人(もしくは現在進行形で)などは、見覚えのある・またはよく知っている風景を楽しめるでしょうし、北京語と広東語が話せる人・ふたつの違いが分かる人と、私のように聞いていて全く違いが分からない人とでは物語の奥行きの感じ方がまるで違うのでしょうけれど、行ったことも言語も知らない自分でもそれなりに楽しめました。
90年代~00年代前半にウォン・カーウァイやフルーツ・チャンの映画を観に行ったりしていましたが、これを見て、自分が香港映画は相当ご無沙汰だったことに改めて気付きました。中国も香港もいろんなことがあって、10数年前とはまるで違う街になっていることをこの映画を通じて感じることができたように思います。
あとちょっと細かいことを言いうと、71年に4月号の『児童楽園』がNo.439で、チュンがウェイフォンおばさんからもらった箱いっぱいの『児童楽園』のうち、画面で確認できる最も新しい号はNo.649なので、仮にそれがその当時の新しい号だとして、チュンが海外へ渡ったのが11~12歳ということと照らし合わせると、映画が作られた2014年でのチュンは、だいたい30代半ばあたりと思われます。
となると「俺たちが中学生だったころは彼ら(デザイン事務所の若い連中)の親はまだ顔も合わせてなかったんだ」っていう台詞からして、あの若いのは未成年か二十歳そこそこのバイト風情だったわけですね…。
そんな連中に「あいつ」呼ばわりされたり、年齢は分からないが会社が出来た頃からそこで働いているシンイーも「(あの女色気付いて)プロフィール写真変えちゃったよww」みたいな陰口を職場で言われてるのを見ると、なんかちょっとイヤになりますね(笑)。まぁそんなもんなんでしょうけど(笑)。

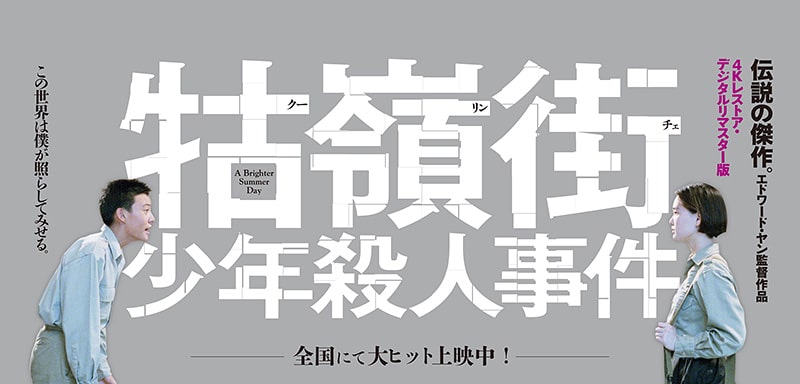





comment