『カイエ・デュ・シネマ・ジャポン/1992年3月号』より
本書に載っていたエドワード・ヤン監督へのインタビューから、物語当時の台湾のことや映画館のシーンについて、また主演の二人を選んだときのことなどを一部抜粋して紹介します。
『牯嶺街少年殺人事件』は1961年の話ですが、60年代という時代を通して台湾という国は、やっと自らの将来について考えるようになったのです。つまり、多くのことが一気に起こったといえますね。外国のたくさんの情報が映画や雑誌や音楽を通して入ってきました。(中略)ご存知のとおり台湾は小さな島です。僕たちは、そうしたさまざまな影響を受けながらその島から逃れることが出来ない。だから島の向こう側、つまり太平洋の向こう側ではいったい何が本当は起こっているのかが無性に知りたくなった。
─そういえば『牯嶺街少年殺人事件』でも、主人公の少年がガールフレンドと映画を見に行くシーンがあり、(中略)でも、私たちは、聞こえてくる声から、それが『リオ・ブラボー』であることがわかりましたが……。
EY (笑)よく判りましたね。あの映画は、実は僕たちのジェネレーションに大きな影響を与えた映画なんです。それにさまざまな種類の西部劇がありましたが、あの映画が特に良かったのは事実です。
(中略)
あのシーンにしたのは、この映画の中に拳銃を扱うシーンがありますね。将軍の息子の家のシーンです。あのシーンとの対応にしたかったんです。それに当時の将軍の家はみんなあのようだったんですよ。国民党であろうと共産党であろうと、将軍の家には、当時は戦争状態に近かったわけですから、ああいう武器をしまって置く場所があったんです。
─彼らもオーディションで決めたのですか。
EY いいえ。僕が十四~五歳の若い女の子を探していることを知っていた友人たちがリサを推薦してくれました。リサを推薦してきた友人が何人もいたので、最初は、皆、冗談で同じことを言っているのかと思いましたが、リサ本人に会ってみると、ミンを演じられるのは彼女しかいないと確信しました。それから、チャン.チェンを捜し出しました。彼に初めてあった時、まだ体が小さかったんです。でも六ヵ月すれば、ちょうど良い大きさになるだろう、とも感じました。それに、何よりも、僕が彼に引きつけられたのは彼の目です。彼の目の表現には、時にはすごく深いものがあるし、また時には、何かはっきりとは形にならない感情を伝えてくれたんです。他の少年たちにはない目の表現があの子にあった、だから、僕はちょうど取りかかっていた企画を一時捨てる気になったんです。いろんなことを思い出すなぁ。
このインタビューは内容についての解説的なものはほとんど載っておらず、また別の特集記事でも前作『恐怖分子』と合わせて撮影手法や音楽の使い方だったりを検証している内容で、『牯嶺街少年殺人事件』のストーリー自体に切り込んでいく内容のものではありませんでした。自分としてもこれ以外に『牯嶺街~』について書かれた本を持っていなかったので余計に理解が足りなかったのかなという気がしています。
2017年版公開時のパンフレットより
先にも書きましたが、このパンフレットの解説・レビューが本当に素晴らしいです。特に2つ挙げるとするならば、映画監督の濱口竜介氏による監督ならではの独特の視点によるレビューと、大学教授で中国語圏の歴史・文化に詳しい三澤真美恵氏による、当時の台湾と台湾に関係する国々についての歴史背景を交えたレビューの2点です。
濱口監督のレビューは、映画パンフでたまに見かけるような「その映画について語っているようで、よく読んだら自分語りだった」とか「資料を見ながらざばっと書いたんだろうな」というような残念なものではなく、私たち一般の観客が分からなくてもやもやしたままだったことや、まず考えないであろう「別の人物からの視点」というところにも言及していて実に面白く、また三澤教授のレビューに関しては、本当に詳しくかつ解りやすく歴史背景を解説してくださっていて、これを知っているのといないのとでは映画の理解度は全く違ってくると思われる濃い内容となっております。
ごく一部分しか取り上げられないのが残念ですが、機会があったらぜひパンフを読んでみてください。なおこのパンフについてもし不満を挙げるとしたら、デザインもうちょっと格好良くならなかったのかな…という1点のみです。『恐怖分子』のパンフがけっこう格好良かっただけに……
『牯嶺街少年殺人事件』4Kレストア・デジタルリマスター版公開時のパンフレット
「<世界>を鍛造した男 あらゆる忘却と想起のために」
濱口竜介(映画監督) より一部引用
(略)
なぜこの映画のことを忘れてしまうのか。いや、そもそも覚えていられないのだ。なぜか。主因は確認するまでもない。まずは暗い。特に序盤から中盤過ぎまで濃い闇が画面を支配し、果たして何が起きているのか、観客は正確に把握することができない。加えて、登場人物の数が多い。更に、その大人数を包括的に捉えようとするキャメラの位置は必然的に遠い。誰が誰か、顔をそもそも認識することができないショット・シーンが映画の大部分を占める。
(中略)
しかし、この近さと明るさの中で捉えられる幾人かも、決して物語をわかり易くばかりはしれくれない。むしろ彼ら自身がこの社会の不可解さに直面するからだ。それは画面外の音として映画内に現れる。
小四、そして小明も、大人たちのいさかいの声を画面外に聞き、どう受け止めてよいかわからないような表情を浮かべる。小四にとってのシェルターのような押入れの外では父母の会話が響く。しかし、その全容は知れず、関与もできない。音の出元が画面外にあるということは、彼らはそれにさわれない、変えられない、ということだ。大人たちにとってのよからぬ事態は、小四たちの関与を拒んで自動的に進行しているようだ。しかし実際には、大人たちも社会を変えることに無力なのだ。
アメリカで先頃発売されたDVDに収録されたオーディオ・コメンタリーでイギリスの批評家トニー・レインズが語るところによれば、『牯嶺街少年殺人事件』の準備段階において「100に及ぶキャラクターのすべてに来歴と、物語が終わって以降どうなるのかについて、膨大なバックストーリーを製作した」「300話分のTVシリーズができるぐらいの物語素材を開発した」ことをヤン自身が証言している。一人の脚本家、演出家としてにわかには信じがたい話だが、作品自体がむしろその証拠となっている。むしろその証言を信じることでのみ、冒頭に掲げたような作品世界の最も周縁にいると言っていい人物にすら性格と、それを表現する機会が与えられているという事態を納得することができる。
「100に及ぶキャラクターのすべてに来歴と、物語が終わって以降どうなるのかについて、膨大なバックストーリーを製作した」ってさらっとすごいことを言っていますが、監督も書かれているように、この映画を見ればそれが本当なんだろうな、ということが分かるというところが『牯嶺街少年殺人事件』のすごさでもあります。
『牯嶺街少年殺人事件』4Kレストア・デジタルリマスター版公開時のパンフレット
「綿密な闇の設計図を玩味する 『牯嶺街少年殺人事件』の歴史的背景」
三澤真美恵(日本大学分理学部中国語中国文化学科教授) より一部引用
(略)
<外省人と本省人>
1945年に日本がアジア太平洋戦争に敗北したことで、台湾は中華民国(蒋介石率いる国民党政府)に接収された。これ以後、中国大陸から国民党政府と共に移り住んだ人々は「外省人」(台湾省以外の出身者)と呼ばれ、その多くは軍人や公務員、教員といった政府関係者とその家族であった。劇中の少年たちの多くも、監督の楊德昌自身も、中国大陸から台湾に渡ってきた外省人である。他方、接収以前から台湾に住んでいた人々、すなわち日本の植民地統治を経験した人々は、「本省人」(台湾省の出身者)と呼ばれた。したがって、1945年10月以後の台湾は、(仮に同じ漢族であったとしても)ついこの間まで敵だった者を今度は同じ社会で生きていく仲間として受け入れなければならないという、外省人にとっても本省人にとっても過酷な再会の場であった。
<冷戦とアメリカの影>
内戦に負けた国民党(中華民国)政府が1949年12月に台湾に全面撤退した直後、1950年1月にはアメリカのトルーマン大統領も台湾海峡に軍事介入しないことを表明した。それは、1949年10月に北京に成立した中華人民共和国(共産党)が台湾を武力「解放」し中華民国(国民党)政府が瓦解する事態になっても、アメリカはそこに介入しないこと、すなわちアメリカが中華民国(国民党)政府を見放すことを意味した。状況を変えたのは、1950年6月の朝鮮戦争勃発である。アメリカ政府は共産主義勢力に対する「不沈空母」としての台湾を確保するため、台湾海峡への介入を決定し、中華民国(国民党)政府との関係強化に転じた。中華民国(国民党)政府は朝鮮戦争の勃発によってかろうじて息を永らえ、アメリカがソ連や中華人民共和国という共産主義勢力を封じ込めるための「反共の防衛ライン」に組み込まれた台湾に、落ち着くことができたのである。
本作に登場する小公園パーラーの天井を飾る旗は、「中華民国」「アメリカ」「国連」の3種類だ。それは、すでに中国大陸は新たに成立した中華人民共和国が実行支配しているにもかかわらず、中華民国(国民党)政府こそが中国を代表しているという幻想が、国連においても承認されていた時代を表している(国連の中国代表権が中華民国から中華人民共和国に入れ替わったのは1971年)。
この引用部分以外にも、戒厳令下での台湾国内の様子がどのようなものだったか、連行された小四の父親のような人たちが何をされたのか、さらにこの映画の元となった実際の事件での、それぞれの家族のその後についても書かれており、3時間56分の『牯嶺街少年殺人事件』“完全版”を紐解く資料のひとつとしても貴重なものとなっています。
というわけで引用ばかりの記事となってしまいましたが、最後に今一度『カイエ・デュ・シネマ・ジャポン/1992年3月号』の特集記事からの一節を引用して締めたいと思います。パンフレット、本当にお金を払って読む価値があるものでしたのでおすすめです。
(略)
『牯嶺街…』の暗闇が齎す印象は、零画面=孔として暗闇のあった『恐怖分子』よりもより深く大きい。この映画の人物構成の基本になっているのは階級別に分かれた少年幫派同士の対立であるが、“二一七”幫を“小公園”幫有志が夜陰に乗じて急襲した時、暗闇は彼らの武器であり、武装そのものでさえあった。そしてその暗闇を裂いた懐中電燈の光りは彼らの憤怒であり、眼そのものでさえあったのだ。小四が“二一七”幫のリーダー、山東の断末魔の苦しみを懐中電燈で検証する時、懐中電燈の光りは正に小四の眼と合体していた。つまり暗闇と光りの織り成す模様は、躍動もしくは焦燥する身体に直結していたのである。
昔はこういうめんどくさいのを有り難がって読んでたんだなぁ(笑)

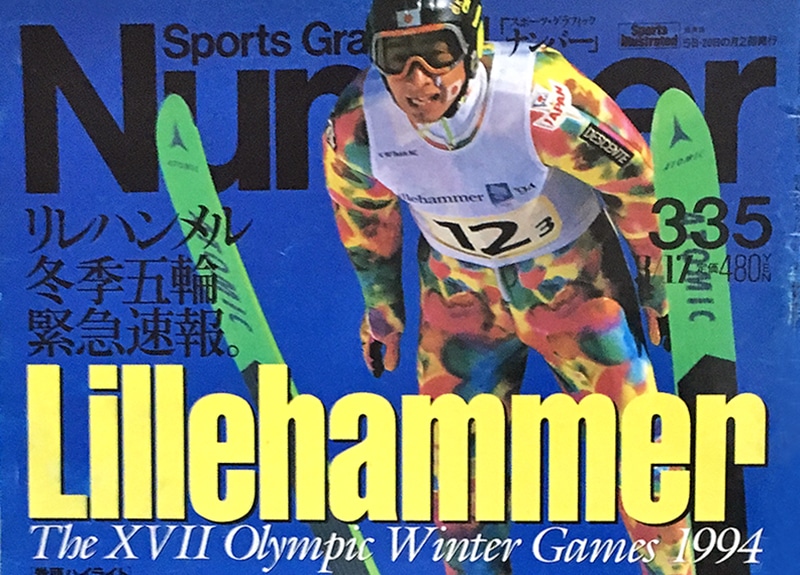



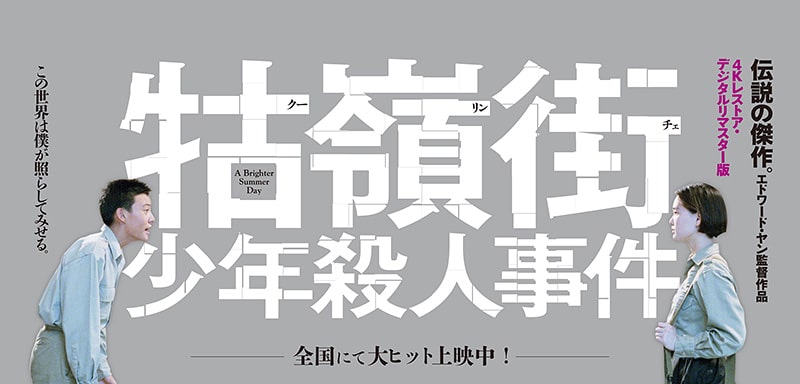
comment